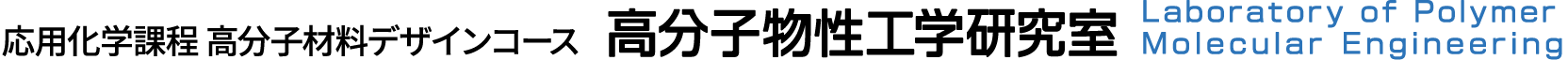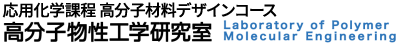リビングラジカル重合の反応過程を動的光散乱法で追跡
動的光散乱法による従来のラジカル重合とリビングラジカル重合のゲル化ダイナミクスの比較に関する論文が、2月16日付けで Polymer 誌に掲載されました。 (Link to publisher)
リビングラジカル重合は、従来のラジカル重合系に特定の連鎖移動剤を添加するだけで単分散に近い直鎖状ポリマーを得ることのできる、有効な合成手段です。共同研究先である京都大学の福田研究室(2005年現在)では、その基本動力学とのグラフト重合による応用研究を展開されています。本研究では、代表的なポリマーであるポリスチレンを例に、従来のラジカル重合とリビングラジカル重合の反応ダイナミクスの実時間観察を試みました。
本研究のそもそもの動機は、2000 – 2004年に展開してきた高分子網目構造およびダイナミクスの特性化にさかのぼります。ゲル中の網目鎖の分子運動に関する研究は、動的光散乱法を例として、最近20年間で精力的になされてきました。特に構造不均一性の解析はゲルのダイナミクスに関する知見を得る上で必要不可欠な手法であり、アクリルアミドゲルやその誘導体、シリカゲル、ポリビニルアルコールゲルなどがサンプルとして用いられてきました。
ところがゲルの構造不均一性を研究していく過程で、種々の散乱法で検知している不均一性の起源に関して疑問がわいてきました。詳細は以前のエントリーに記載していますが、その結論としては、(1)直鎖状高分子に架橋を導入する「ランダム架橋」の場合でも、ゲルの網目構造は普遍的に不均一である事、(2)アクリルアミドゲルのようにモノマーと架橋剤を共重合して得られるゲルの場合、散乱法で観察される不均一性は、ゲルの本質である揺らぎ凍結の不均一性に加えて、クラスタードメインの形成や反応過程に依存した不均一性が加わる事があげられます。

このように、ポリマーを出発原料とするゲルの場合、より不均一性の小さいゲルを調整する事ができるわけですが、はたしてモノマーを出発原料として均一な網目を構築する事は可能なのでしょうか?そこでリビング重合法が候補としてあがりました。
リビング重合法は単分散に近い高分子を得る有効な手法ですが、モノマーを出発原料とするゲル系に適応して果たして意味があるのでしょうか?仮に単分散な鎖が反応過程で生成できたとして、それらはたった一つの架橋点に出会うだけで分子量が2倍・3倍に増大します。よって鎖長に分布が生じることは容易に想像が付きます。本論文では、その答えを結論で述べています。詳細は論文をご覧下さい。
本論文は大きく分けて2部から構成されています。前半は直鎖状高分子の反応過程解析で、重合過程で観察された散乱強度の極大とその後の更なる増大の原因を、静的・動的光散乱の組み合わせによって実現する「揺らぎの分離」によって詳細に分析しています。


後半は架橋系のダイナミクス解析で、(1)スローモードの発散がゾルゲル転移に普遍的である事と、(2)スローモードの振幅が二つの重合法で大きく異なる事を述べています。このように動的光散乱法で測定したデータを、揺らぎ分離解析により詳細に解析することで、複雑系に分類される架橋系材料の構造と分子運動に関する知見を得ることができます。