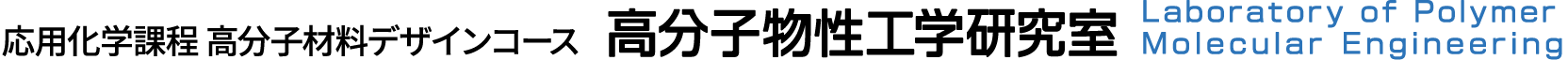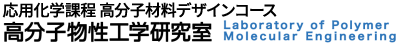二種類の不均一性に関する論文が、米Macromolecules誌に掲載されました
米Macromolecules誌に受理された論文が、2003年7月12日付けで掲載されました。
ブラウン運動でおなじみのように、溶液中の高分子鎖は熱運動しているため、非常にミクロなレベルでは、時間と共に濃度が微妙に変化しています。これを濃度揺らぎといい、散乱法ではこの変化をうまく検出して構造や運動に関する知見を得ることができます。濃度揺らぎは多かれ少なかれミクロな物性に影響しますが、一般的な高分子溶液においてはこの濃度のズレは時間平均によって相殺されるため、特に問題として取り上げることはありません。
しかしながら、高分子ゲルの場合、この濃度揺らぎが架橋によって凍結されるため、濃度揺らぎが恒久的に保持されることになります。ゲルの場合は、濃度揺らぎを時間平均で解消する事ができないため、結果として空間的にも著しい濃度揺らぎが生じます。(下の模式図)

これをゲルの構造不均一性と言いますが、多くの研究で論じられている不均一性は必ずしもこれを指しておらず、適切な実験系に対して評価ができているとは言えません!
例えば、モノマーを出発原料にして架橋剤とラジカル共重合するゲル調整法がありますが、この場合前述の不均一性の話題以前に、(1)ミクロゲルの形成、(2)分子内架橋反応、(3)著しい架橋点の空間分布を生じるため、こういった試料を使ったゲルの不均一性の議論は十分とは言えません。スチレン・ジビニルベンゼン系、アクリルアミド・ビスアクリルアミド系などはその典型例と言えます。

本論文では、モノマーおよびポリマーを出発原料にする二種類のゲルを作成し、散乱法を用いて構造とダイナミクスの解析を行い、不均一性の起源について検討してみました。
Studies on Two Types of Built-in Inhomogeneities for Polymer Gels: Frozen Segmental Concentration Fluctuations and Spatial Distribution of Cross-Links Tomohisa Norisuye, Yusuke Kida, Naoki Masui, and Qui Tran-Cong-Miyata, Yasunari Maekawa, Masaru Yoshida and Mitsuhiro Shibayama, Macromolecules 2003, 36, 6202