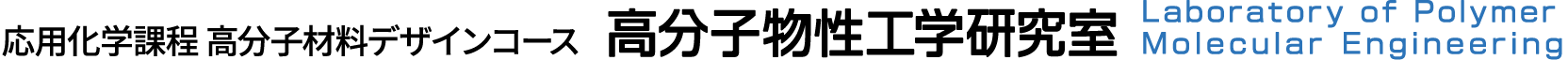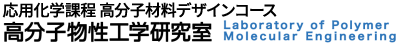「超強酸を触媒とした有機修飾型シリカクラスターのDLSおよびAFM解析」に関する論文がMacromolecules誌に掲載されました
2007年4月14日付けで、「超強酸を触媒とした有機修飾型シリカクラスターのDLSおよびAFM解析」と題する論文が米Macromolecules誌に掲載されました。
高分子を3次元的に架橋した高分子ゲルの構造は、しばしば編目のようなモデルで説明されますが、多くの場合、モデル図のような構造形成は行われていません。極端な例で説明すると、モノマーを出発原料としてゲル化を開始した場合、モノマーはダイマーへ、ダイマーはトリマーもしくは環状の小粒子へ、そしてこれらが化学結合した結果、2次的な粒子が形成します。この粒子は、溶媒に対してほどよい親和力があり、粒子間に適度な斥力ポテンシャルが作用している間に安定に存在し、その間粒子成長することができます。逆に、この安定性が破られる場合には、これ以上成長できず、凝集、沈殿、相分離が起こるでしょう。
表面が電荷を帯びたシリカクラスター粒子は、触媒の作用によって安定化されていますが、重合の後期過程に入るとさすがにその効力がなくなり、また粒子が大きいために不安定化します。このとき系は極度に増粘し、粒子は凝集し、最終的にゲルになります。これが実際のゲル化です。(シリカ系だけでなく、おそらくモノマー開始のラジカル重合系も類似した結論が得られるでしょう。)ところがこのような議論は、これまでのゲル研究では皆無に近く、はじめて具体的に論じました。(正確には、古い研究ではこの事は理解されていたよう思えますが、現代のゲル研究では、あまりに異なった模式図(理想的なネットワークと架橋点)が使われています。)

シリカゲルのゲル化過程は、用いる触媒に大きく依存する事はこれまでよく知られていました。私たちはこれまで、酸触媒系で効果的な粒子成長(本来塩基で可能)を実現するために、ヘテロポリ酸を利用してきました。そのアプリケーションとして、プロトン伝導体をシリカクラスターに内包させ、最終的にゲルにさせると、伝導体を多く含んだプロトン伝導膜へと発展します。ただし、この伝導特性は、必ずしも膜の構造特性で決まらず、また実際に導入された伝導体濃度で決まるわけでもないため、本研究では、その反応プロセルを動的光散乱(DLS)および原子間力顕微鏡(AFM)で追跡しました。
DLSは、溶液中で膨潤した粒子ダイナミクス解析に有効な方法です。そのサイズ分布も評価できると考えられていますが、平均サイズ(第一キュムラント)と比較して、その厳密性に乏しい欠点(キュムラント展開の曖昧さや、逆ラプラス悪条件問題)があります。その一方でクラスターサイズ分布を調べたり、個々のクラスターを可視化する目的でAFMは有効です。さらにAFMからは収縮状態のクラスターサイズが得られるため、膨潤・収縮状態のクラスターサイズを比較することで、「密に成長したクラスター」や「凝集で密度が低くなる様子」など様々なゲル化メカニズムに関する知見が得られると期待されます。本研究では、プロトン伝導体濃度の構造および伝導特性に対する最適値について論じました。
詳細はこちらをご覧ください。