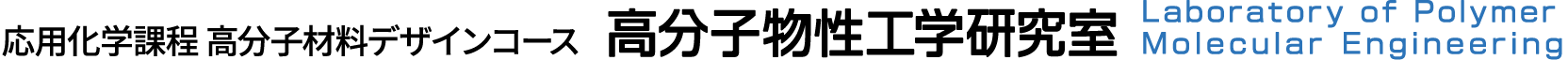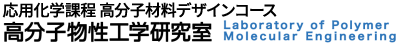Winnipeg Ultrasound Forum 2024
2024年7月15日(月)から26日(金)にカナダのマニトバ大学で開催されたWinnipeg Ultrasound Forum 2024に参加し、講演を行なってきました。
今回のワークショップはただの国際学会ではなくて、第一線で活躍する世界の超音波研究者が多く集まる会であり、私にとって非常に重要な学会でした。というのも、私が超音波研究を始めるに至った動機がこのマニトバ大学にあり、最先端の優れた研究論文を発表されている魅力的な研究者たちに会える機会であったためです。
そもそも、私が超音波研究を始めたのは、カナダのマニトバ大学のJohn Page先生に手紙を書き、2004年から1年間海外留学したことでした。John Page先生に快く受け入れてもらい、私はカナダで超音波を学ぶ機会を得ました。より正確にいうと、当時の私の恩師である宮田貴章先生(Qui Tran-Cong-Miyata名誉教授)が学会で、そののちに私の友人となるJohn Page研のAnatoliy Strybulevych博士と出会い、恩師を通じて紹介してもらったことがきっかけでした。
- from iPhone
私は今、新しい独自の超音波技術を活用したナノ粒子やミクロン粒子の研究を行うに至っています。この研究に至る背景には、カナダで学んだことが大いに関係しています。Page教授の研究室では、ミリメートル程度の大きさの粒子を扱っていましたが、これは超音波で粒子を伝播する波動を非常にスマートな方法で研究するためでした。Page教授の研究室は、最近流行となっているメタマテリアルやAndersonローカリゼーションを、世界に先駆けて音波で研究したことで有名な研究室です。そのため、私が帰国した後も、次々とポスドクや客員研究員が訪れ、John Page教授の元で超音波物理を学んだと聞きます。
今回のワークショップはそんなJohn Page研の門下生が一度に集まり、交流する学会でした。この「一度に集まる」という観点では奇跡に近い状態です。二週間のワークショップは、毎朝2名の講演から始まり、続いてみんな集まって午前中に論文のレビューを行い、午後はいくつかのテーマで共同で実験を行うものでした。私が研究しているナノ・ミクロン粒子と比較してかなりスケールが大きい実験になるのですが、音波の多重散乱や粘弾性特性解析としてどれも非常に興味深い実験でした。John Page教授に加えて、オーガナイザーである、Sorbonne 大学のBenoit Tallon博士とLe Mans 大学のMaxime LANOY博士に感謝します。
個人的に良かったことは、論文誌で拝見する著名な研究者が集まったことでした。今回の交流により、新しい共同研究の芽も複数生まれました。John Page先生は定年退職されましたが、その門下生たちは、物理や化学や食品や医療など、さまざまな分野に広がってJohn Page先生の意思を引き継いでいます。
今回、もう一つ刺激的であったのは、海外の研究者との出会いを通じて、日本の研究や教育のあり方について考えさせられることが多かったことです。若い頃は先行きが見えないことから、目の前の課題である大学の単位や卒業、就職にとらわれがちです。一方で、例えば修士を卒業した24歳での就職は、まだまだ人生の序盤であるため、就職すること自身がゴールではないはずです。その意味で、就職にとらわれず、むしろドクター(博士後期課程)を終えた後に、さらに海外にポスドクとして世界を渡り歩き、もっと広い視点も持って自分の人生を有意義なものにするのも良いのではと改めて思いました。民間企業で働くことで役に立つ人間になる(親にお金を入れる)ことも大切ですが、企業のために行う研究ではなく(給与をもらう代償として仕事の命令を待つのではなく)、新しい世界を開拓するために行う自身の興味で動き、好奇心を仕事にすることや、(一企業の歯車ではなく)新しい技術を自身で作り上げることも大切ではないでしょうか?日本人の先生と話しているとなかなかこのような話は出てこないのですが、海外の先生方と話しているともっともっと多彩で希望に満ち溢れた冒険の話が出てきます。今回の話の中で、20年前に自分もそうだったなぁーというのをリアルに思い出しました。私にも当時、世界にない技術を作るんだ!という強い想いがありました。研究者になることに関しては、20年前の大学教員の狭き門は変わりつつあり、今では博士支援制度(授業料無料で博士号が取得できて給与までもらえる)が充実しています。将来に希望を持った人がさらに増えてくれると私も嬉しいです。
則末